| 金封と水引 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 金封について | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
[結びきりと花結び] |
|||||||||||||||||||||||||||||||
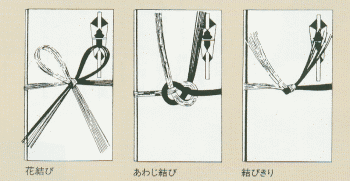
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| [お金包みのたたみ方]
上包みの上下の端は裏へ折り、慶事では下側の折り返しを上にして、弔事では下にして重ねます。慶事で下側の折り返しを上げるのは、運が上がるように、または晴れ晴れと目を上げて喜びをあらわすという意味です。弔事では上側を下げ、目を伏せて、悲しみをあらわす、と覚えます。まちがえやすいので気をつけましょう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
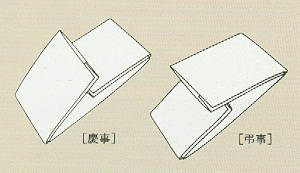
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| [冠婚葬祭の表書き] 毛筆で丁寧に、慶事は喜びで濃く鮮やかに、弔事は悲しみに薄墨でしっかりと書きます。 表書きは上段中心へ大きめに、氏名は下段中心に小さめに書きます。 中袋には表に金額、裏に自分の住所氏名を書きます。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 水引について | |||||||||||||||||||||||||||||||
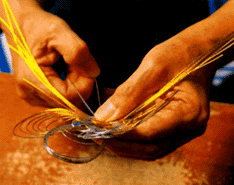 |
南北に伸びる長野県の南、天竜川をはさんで、南アルプスと中央アルプスに抱かれた伊那谷の中央に位置する城下町“飯田”。 アルプスからの清流は、段丘を刻んで果物がたわわに実る肥沃な土を育み、あふれる緑は折々の色彩をまとつて豊かな表情を見せています。こうした風土の利を生かし、飯田は古くから水引のふるさととしての伝統を受け継いできました。 人と人、心と心を結ぶ水引。和紙が織りなす雅で繊細な技は、忘れかけた日本の心そのものかもしれません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 飯田水引、事始め。 飯田水引の始まりは、元禄年間(1700年頃)のこと。当時の飯田領主堀侯が凍豆腐を将軍に献上する際、「クレナイ」の儀式に習って紅白の水引を輪結びにしたことに幕を開けます。しかしながら江戸時代は、ほとんどの人が留(まげ)を結っていましたから、当初は留を結うための紙紐である元結(“もとゆい”または“もつとい”“もとぎ”とも言う)が主流で、ほぼ同様の製法で作られる水引は、副業に過ぎませんでした。飯田の元結はもともと品質の優れていることで定評がありましたが、美濃から招かれた紙漉き職人・桜井文七が和紙製造にさらに改良を加えると、元結の代名詞『文七元結』として全国にその名を知られるようになりました。ところが断髪令によって元結の需要は激減し、代わって副業だった水引と水引工芸が飯田を代表する産業として、発展を遂げることになったのです。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 【時代は流れても、手のぬくもりは生きている。】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料提供:佐々木水引工業株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||

